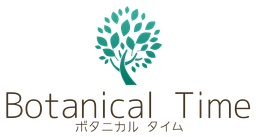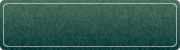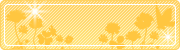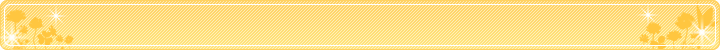- ホーム
- ボタニカルゆったりブログ
ボタニカルゆったりブログ
アロマのコラムはもちろん、私たちの心と体について、解剖学や健康学、女性学を絡めた豆知識も紹介していきたいと思います
ランチの後、電車の中など、少しの時間でさっと読めるものにしますので、時々、チェックしてみて下さいね
【アロマの日カウントダウン③】
ローズ・オットー ― 心を満たす香り、香り文化の象徴
2025/10/31

✴︎アロマの日カウントダウン✴︎
11月3日の「アロマの日」に向けて、 3日間、特別な精油をひとつずつご紹介しています。 深まる秋に寄り添う香りたちを、どうぞお楽しみください。
ローズ・オットー ― 心を満たす香り
ローズ・オットーは、バラの花から水蒸気蒸留で抽出される最も希少な精油で、 “香りの女王”とも称されます。
古来より香水や王侯貴族の儀式に用いられ、心を豊かに満たす存在として知られています。
精油のプロフィール
学名: Rosa damascena
科名: バラ科 抽出部位: 花
抽出法: 水蒸気蒸留法
主な産地: トルコ、ブルガリア、モロッコ
繊細な花びらから少量しか抽出できないため、大変高価ですが、
その香りは深く、幸福感と満足感に満ちています。
心への作用 ― 幸福感と女性性をサポート
ローズ・オットーは、心に安らぎと喜びを与え、 不安や緊張、悲しみをやわらげる作用があります。
また、自己肯定感や女性性を高める香りとしても知られ、
「香り文化の象徴」として、多くの人に愛され続けています。
体への作用 ― ホルモンバランスと血行のサポート
ローズ精油には、ホルモンバランスを整える作用や、血行促進効果もあります。
更年期や月経前の不調、冷えやこわばりへのケアにもおすすめです。
おすすめの使い方
芳香浴: ディフューザーで。特別な日のリラックスに。
トリートメント: キャリアオイルに1滴〜2滴を加えて肩やデコルテに。
アロマバス:少量をオイルに混ぜて湯船に加えると、心と体をやさしく満たします。ブレンド例: ネロリ、ラベンダー、スイートオレンジとの相性が良好。
注意点
・妊娠初期は使用を避けてください。
・肌に塗布する場合は必ず希釈してください。
ローズ・オットーがもたらす“心の満たされ感”
ローズ・オットーは、香りを嗅ぐだけで心が満たされ、幸福感を感じさせてくれます。
忙しい日々の中で、自分を大切にする時間を作りたいとき、 深く豊かな香りが、心と体を包み込むように優しく寄り添います。
――アロマの日、心もからだも、香りとともに満たされるひとときをお楽しみください。
【アロマの日カウントダウン②】
ネロリ ― 心をやわらげる花の香り
2025/10/31

✴︎アロマの日カウントダウン✴︎
11月3日の「アロマの日」に向けて、 3日間、特別な精油をひとつずつご紹介しています。 深まる秋に寄り添う香りたちを、どうぞお楽しみください。
ネロリ ― 心をやわらげる花の香り
ネロリは、ビターオレンジの花から抽出される希少な精油で、 その優雅で甘くほろ苦い香りは、古くから“心を癒す香り”として愛されてきました。
名前の由来は、17世紀のイタリア貴族ネロリ公爵夫人の名前から。
彼女が香水として愛用していたことから「ネロリ」と呼ばれるようになりました。
精油のプロフィール
学名: Citrus aurantium var. amara
科名: ミカン科
抽出部位: 花
抽出法: 水蒸気蒸留法
主な産地: モロッコ、チュニジア、エジプトなど
ビターオレンジの花から丁寧に蒸留されるネロリ精油は、 希少で高価ですが、その香りは深く心に届きます。
心への作用 ― 不安や緊張をやわらげる
ネロリには、自律神経を整え、心の緊張をやわらげる作用があります。
ストレスや疲れで心が重くなるとき、そっと寄り添い、穏やかな安心感をもたらします。
眠れない夜や気持ちがざわつくときにもおすすめ。
深呼吸とともに香りを嗅ぐだけで、心が落ち着き、優しい気持ちに包まれます。
体への作用 ― ホルモンや循環をサポート
ネロリ精油は、ホルモンバランスを整える働きが知られています。 更年期や月経前の不調、情緒の揺らぎにも寄り添い、 からだのめぐりや疲労感の軽減にも役立ちます。
おすすめの使い方
芳香浴: ディフューザーで。リラックスしたい夜や朝の目覚めに。
トリートメント: ホホバオイル10mlに1滴〜2滴をブレンドし、手首や肩などに。
アロマバス: キャリアオイルに混ぜて湯船に加えると心と体をやさしく包みます。
ブレンド例:ラベンダー、ローズ、スイートオレンジとの相性が良好。注意点
・妊娠初期の使用は避けてください。
・肌に直接塗布する場合は希釈を必ず行ってください。
ネロリがもたらす“心のやわらぎ”
ネロリの香りは、忙しい日常の中でも心をそっとほぐしてくれます。
「大丈夫、少し休もう」と語りかけてくれるような優しさがあります。
香りが心の深くに届き、やわらかな安心感を与えてくれる
―― ネロリは、心を解きほぐす“花の精油”です。
【アロマの日カウントダウン①】
スイートマジョラム ― やさしく包み込む、心と体の温もり
2025/10/31

✴︎アロマの日カウントダウン✴︎
11月3日の「アロマの日」に向けて、 今日から3日間、特別な精油をひとつずつご紹介していきます。 深まる秋に寄り添う香りたちを、どうぞお楽しみください。
マジョラム ― やさしく包み込む、心と体の温もり
古代ギリシャでは「幸福のハーブ」として花嫁の冠にも使われたマジョラム。
その名は “joy of the mountains(山の喜び)” に由来すると言われています。
ハーブらしいやわらかな香りの中に、どこか甘く温かみを感じるこの精油は、 冷えや緊張、心のこわばりをやさしくほどいてくれる存在です。
精油のプロフィール
学名: Origanum majorana
科名: シソ科
抽出部位: 花と葉
抽出法: 水蒸気蒸留法
主な産地: エジプト、フランス、スペインなど
地中海沿岸に自生する多年草で、温暖な風と太陽のもとで香り高く育ちます。
見た目は控えめながら、その精油には「深い安心感」と「体を温める力」が宿っています。
心への作用 ― 不安や緊張をやさしく解きほぐす
マジョラムは、神経の高ぶりを鎮め、心を落ち着かせる作用が知られています。
過度なストレス、孤独感、悲しみなどで心が疲れたとき、 まるで温かな毛布に包まれるような安心感をもたらします。
眠れない夜、考えすぎてしまうときにもおすすめです。
副交感神経を優位にし、自然な眠りへと導いてくれます。
体への作用 ― 巡りを助け、こわばりを緩める
マジョラム精油には、血行を促進し、体を内側から温める作用があります。
特に冷えによる肩こり・生理痛・筋肉のこわばりなどのケアに効果的です。
また、自律神経のバランスを整える働きもあるため、 更年期や月経前の不調、情緒の揺らぎにもやさしく寄り添ってくれます。
おすすめの使い方
芳香浴: 寝る前にディフューザーで。心地よい眠りをサポート。
トリートメント: ホホバオイル10mlに1〜2滴をブレンドし、肩やお腹をやさしくマッサージ。
アロマバス: キャリアオイルに混ぜてお湯に加え、全身をじんわり温めて。
ブレンド例: ラベンダー、スイートオレンジ、クラリセージなどとの相性が良好。
注意点
・妊娠初期の使用は避けてください。
・血圧を下げる作用があるため、低血圧の方は少量から様子を見て使用を。
・鎮静作用が強いため、集中が必要な作業前の使用は控えめに。
マジョラムがもたらす“ぬくもりの記憶”
忙しい毎日の中で、私たちは知らず知らずのうちに心と体を固くしてしまいます。
マジョラムの香りは、そんな緊張をそっとゆるめ、
「大丈夫、焦らなくていいよ」と語りかけてくれるような優しさがあります。
冷えた体に血がめぐるように、 香りが心にぬくもりを取り戻してくれる
―― マジョラムは、心身を温め、やさしい眠りへと導く“癒しの精油”です。
🕊️明日は、心をやわらげる花の香り「ネロリ」をご紹介します。
11月3日は『アロマの日』。香りと心がつながる時間を。
2025/10/31
11月3日は「アロマの日」。
日本アロマ環境協会(AEAJ)が、香りを文化として広めていくことを目的に制定した記念日です。
私たちの暮らしの中に、香りはいつもそっと寄り添っています。
季節の変わり目に気持ちを落ち着けたいとき、眠る前に深呼吸をしたいとき——
精油の香りがふっと心をほぐしてくれる瞬間があります。
サロンではこの季節、深まる秋にぴったりな香りを中心にトリートメントを行っています。
ウッディ系やスパイス系の香りが、冷えや緊張をやわらげ、心まであたたかく包み込んでくれます。
「アロマの日」をきっかけに、
少しだけ香りに意識を向けてみませんか?
あなたの心とからだに寄り添う“今の香り”を一緒に見つけていきましょう。
11月3日の「アロマの日」に向けて、
明日から3日間、特別な精油をひとつずつご紹介します。
深まる秋に寄り添う香りたちを、どうぞお楽しみください。
第3回 家庭での血圧測定と、上手なつきあい方
―「数字」に振り回されない習慣づくり―
2025/10/23

血圧を測る習慣をつけるなら、家庭での測定がいちばんおすすめです。
病院よりも落ち着いた状態で測れるため、
より「ふだんの自分の血圧」に近い数値がわかります。
家庭での測定のポイント
・測定のタイミング:
朝起きて1時間以内、排尿後・朝食前・服薬前に測るのが理想です。
夜は寝る前に、1日の締めくくりとして。
・姿勢:
椅子に座って、背もたれに軽くもたれ、
腕を心臓の高さに保ちましょう。
・環境:
寒すぎたり暑すぎたりすると、血圧は変動します。
リラックスできる室温で、静かに深呼吸してから測りましょう。
続けるコツと心の持ち方
記録は手帳でもアプリでもOK。
日付や時間とともに数値を残していくと、
体調の波や生活のリズムが見えてきます。
ただし、毎回の数値に振り回される必要はありません。
少し高い日があっても、「今日は少し疲れているのかも」と受け止めるくらいで十分です。
血圧は“結果”ではなく、“からだのメッセージ”なのです。
香りでサポートする「測定のひととき」
血圧を測る前に、深呼吸をして気持ちを落ち着けるだけでも数値は安定しやすくなります。
お気に入りの香りをそっと漂わせるのもおすすめです。
ラベンダーやベルガモット、マンダリンなどの精油は、
呼吸を深め、自律神経のバランスを整えてくれます。
「測る時間」が“自分と向き合うリラックスタイム”になるように。
それが、血圧と上手につきあういちばんの秘訣です。
シリーズまとめ
血圧は「数字の問題」ではなく、「自分を知るためのサイン」。
毎日の小さな習慣が、からだと心を整える第一歩になります。
どうぞ無理なく、ご自身のペースで続けてみてくださいね。
第2回 血圧を知ることの意味
―変動の裏にある、からだとこころのサイン―
2025/10/23

毎日測っていると、血圧の数値は日によって意外と変わるものです。
「昨日より高い」「今日は低い」と気になることもありますが、
その変動こそが“からだの声”を映し出しています。
血圧は、日々のコンディションの鏡
血圧は常に一定ではなく、1日の中でも上がったり下がったりしています。
朝は活動に備えて自然に上がり、夜はリラックスとともに下がる――
これが健康的なリズムです。
しかし、ストレスや睡眠不足、塩分の摂りすぎ、
ホルモンバランスの変化などによって、そのリズムが乱れることがあります。
たとえば「最近、寝つきが悪い」「仕事が立て込んでいる」
そんなとき、血圧がやや高めに出ることも珍しくありません。
高血圧・低血圧、それぞれの背景
・高めの血圧は、血管に強い圧がかかっている状態。
長く続くと血管や心臓への負担が大きくなります。
・低めの血圧は、血流が全身に十分届きにくい状態。
冷えや立ちくらみ、疲れやすさなどにつながることもあります。
どちらも「悪い」「良い」ではなく、
その人の体質や生活リズムに合った“ほどよい範囲”を知ることが大切です。
「知ること」が、ケアの第一歩
血圧を定期的に測って数字を記録していくと、
「このくらいが自分の安定した数値だな」と感覚的にわかってきます。
それが、自分の健康状態を見守る「基準点」になります。
数字に一喜一憂せず、変化を“気づきのサイン”として受け取る。
それが“血圧を知ることの意味”です。
次回は、家庭での血圧測定のコツと、
上手に続けるためのヒントをお伝えします。
第1回 血圧ってそもそも何?
―毎日測るだけでも意味がある理由―
2025/10/23

最近、健康番組で「血圧は測るだけでも意味がある」という特集を見かけました。
その言葉に惹かれて、私も3日前から毎日、血圧を測るようになりました。
試しに周りの友人たちに「血圧、測ってる?」と聞いてみると、思った以上に「毎朝測ってるよ」「最近はアプリで記録してる」など、意識的に管理している人が多くて少し驚きました。
年齢的にも、そろそろ気にしておくタイミングなのかもしれませんね。
血圧とは?
血圧とは、血液が血管の壁を押す力のこと。
心臓がポンプのように全身へ血液を送り出すときに生じる「圧力」です。
上の数値(収縮期血圧)は心臓がぎゅっと収縮して血液を送り出すときの圧力、
下の数値(拡張期血圧)は心臓が休んでいるときの圧力を示しています。
この2つのバランスが取れていることが、
全身に酸素や栄養をスムーズに届けるためにとても大切なのです。
なぜ年齢とともに大切になるの?
血管は年齢とともに少しずつ弾力を失い、
血液の流れに抵抗が生じやすくなります。
そのため、若いころは正常でも、
40代・50代になると自然と血圧が上がりやすくなる傾向があります。
また、ストレス・睡眠不足・塩分の摂りすぎなど、
生活習慣の影響も受けやすいもの。
だからこそ「定期的に測る」ことが、
自分の体調の“今”を知る大切な手がかりになります。
「測るだけ」で変わること
面白いことに、血圧は“測る”という行動自体が
健康意識を高めるきっかけになるそうです。
数字を見ることで、
「今日はちょっと高めだな」「最近よく眠れていないかも」
と、生活を振り返る習慣が自然と身につくのです。
特別なことをしなくても、
まずは1日1回、同じ時間に測ってみる。
それだけでも十分な健康ケアの第一歩です。
次回は、血圧の変動と体調の関係について。
1日のうちでも変わる血圧のリズムや、
ストレス・ホルモンとのつながりをお話しします。
どうぞお楽しみに。
血圧を知ることから始めるセルフケア
―からだと心の“今”を見つめる3回シリーズ―
2025/10/23

年齢を重ねるとともに、少しずつ気になってくる「血圧」。
数字として見ることはあっても、
その意味や変化の背景までは意外と知らないものです。
先日、健康番組で「血圧は測るだけでも意味がある」という言葉を耳にしました。
それをきっかけに毎日測り始めてみると、
体調や気分の小さな変化に気づけるようになり、
自分のからだと向き合う時間が少し豊かになったように感じます。
血圧を“知る”ことは、健康を守るだけでなく、
日々の暮らしを丁寧に感じ取るための小さな習慣でもあります。
このシリーズでは、
血圧の基本から、測ることの意味、そして続けるコツまでを3回にわたってお届けします。
シリーズ内容
▶ 第1回:「血圧ってそもそも何? ―毎日測るだけでも意味がある理由―」
血圧の基本的な仕組みや、上と下の数値の違いについて。
年齢とともに血圧が変化する理由もわかりやすく解説します。
▶ 第2回:「血圧を知ることの意味 ―変動の裏にある、からだとこころのサイン―」
毎日の変動から見えてくる体調やストレスとの関係。
“知ること”が健康ケアの第一歩になる理由をお伝えします。
▶ 第3回:「家庭での血圧測定と、上手なつきあい方 ―『数字』に振り回されない習慣づくり―」
正しい測定方法と、続けるためのコツ。
香りを取り入れたリラックスの工夫もご紹介します。
血圧を“日々の自分を感じ取るツール”として捉えること。
その意識が、健やかなこころとからだにつながります。
どうぞ、ご自身のペースで読み進めてみてください。
明日から3回にわたって、血圧と健康の関係について少しずつお話ししていきます。
毎日の暮らしの中で、自分のからだを見つめるきっかけになれば嬉しいです。
カモミール(ジャーマンカモミール)― 消化器と神経を整える代表的鎮静ハーブ
2025/10/18
カモミール(Chamomile)は、古くからヨーロッパの家庭で薬草として用いられてきたハーブです。
特にジャーマンカモミール(Matricaria chamomilla)は、炎症を鎮め、消化器系・神経系のバランスを整える作用で知られています。
■ 主な有効成分と薬理作用
* アズレン(Azulene)・カマズレン(Chamazulene)
精油成分の一種。
抗炎症・抗アレルギー作用があり、胃粘膜の炎症や皮膚炎の改善に寄与します。
蒸留中に生成される青色の成分で、鎮静・抗ヒスタミン作用も確認されています。
* ビサボロール(α-Bisabolol)
抗菌・鎮静・抗潰瘍作用をもつ成分。
胃酸過多や胃炎、PMSなどの不快症状を和らげるとされます。
* アピゲニン(Apigenin)
フラボノイドの一種で、中枢神経に穏やかに働きかける鎮静作用を持ちます。
ストレス性の不眠や緊張性頭痛の軽減が期待されています。
■ 生理・臨床的な作用領域
* 消化器系への作用
胃腸粘膜の炎症を抑え、蠕動運動を整えることから、消化不良・胃痛・鼓腸感などに適応されます。
また、ストレスによる胃の不快感(機能性ディスペプシア)にも有効とされます。
* 神経系への作用
軽度の不安・緊張・不眠に対する鎮静効果が報告されています。
ドイツでは、不安神経症に対する緩和目的でハーブティーまたはチンキ剤として使用されています。
* 皮膚・粘膜への作用
抗炎症作用により、湿疹・かゆみ・アトピー性皮膚炎のサポートにも利用されます。
内服だけでなく、外用(ハーブ浴や湿布)にも応用可能です。
■ 味と香りの特徴
カモミールティーは、リンゴを思わせる甘い香りが特徴です。
これは成分アンゲリカ酸エステルによるもので、香り自体にも鎮静作用があるといわれています。
味はまろやかでやさしく、苦味が少ないため、ハーブティー初心者でも飲みやすいのが特徴です。
ブレンドする場合は、ペパーミント(消化促進)やレモンバーム(神経安定)と相性が良く、 リラックス系・消化器系ブレンドのベースハーブとしてもよく用いられます。
■ 摂取の目安と注意点
1日1〜3杯を目安に、沸騰直後の湯で3〜5分抽出します。
キク科アレルギーのある方は注意が必要です。
また、妊娠初期の多量摂取は避けましょう(子宮収縮作用の可能性があります)。
■ メディカルハーブとしての位置づけ
カモミールは、神経性胃炎・不眠・月経痛・皮膚炎など幅広い領域でエビデンスが蓄積しているハーブです。
穏やかな作用ながら、長期的に体質を整える目的でも使用できるため、 日常のセルフケアに取り入れやすい“基本の鎮静ハーブ”といえます。
次回は、消化促進と頭痛緩和に優れたペパーミント(Mentha piperita)をご紹介します。
作用機序の違いを理解することで、症状や体質に合ったハーブブレンドが選びやすくなります。
フランキンセンス精油 ― 深い呼吸と心の静寂をもたらす香り
2025/10/17
古代エジプトの神殿で焚かれ、聖書にも登場する「フランキンセンス(乳香)」。
その名は「真の香り(franc encens)」に由来すると言われています。
心を鎮め、深い呼吸を促すその香りは、今なお“神聖な精油”として世界中で愛されています。
精油のプロフィール
* 学名:Boswellia carterii(または Boswellia sacra)
* 科名:カンラン科
* 抽出部位:樹脂
* 抽出法:水蒸気蒸留法
* 主な産地:ソマリア、オマーン、エチオピアなど
フランキンセンスの樹木に傷をつけると、乳白色の樹脂がゆっくりと滲み出します。
それを乾燥させたものが「乳香」と呼ばれる天然樹脂。
その樹脂から丁寧に蒸留して得られる精油は、古代から現代に至るまで、人々の心に“祈り”のような静けさをもたらしてきました。
心への作用 ― 深呼吸と心の静寂を取り戻す
フランキンセンスの香りは、心を穏やかに鎮めながらも、意識をクリアに導きます。
不安や緊張、過去への執着で心が落ち着かないときに、呼吸を深め、心のざわめきを静かに整えてくれる香りです。
瞑想やヨガ、就寝前のリラックスタイムにも最適で、
「香りを吸い込むだけで、胸の奥に静けさが広がる」ような深い安堵を感じる方も多いでしょう。
体への作用 ― 呼吸とお肌のサポートに
* 呼吸器系の不調をやわらげ、呼吸を深める作用
* 免疫をサポートし、風邪や喉の不快感のケアに
* 細胞の再生を助け、エイジングケアに適したスキンケア効果
お肌への働きも注目されています。
フランキンセンスは、乾燥・たるみ・小じわなどの年齢サインに対して、
肌のキメを整え、うるおいを保ちながらハリを与える作用があります。
おすすめの使い方
* 芳香浴:深いリラックスや瞑想の時間に。
* フェイシャルケア:ホホバオイル10mlに1滴をブレンドし、夜のスキンケアに。
* アロマバス:無水エタノールやキャリアオイルに混ぜてお風呂に。静かな時間に包まれながら心身をリセット。
* 呼吸サポート:ユーカリやラベンダーとのブレンドもおすすめ。
注意点
・妊娠初期の使用は控えてください。
・樹脂系精油のため、精油が濃い場合は肌への直接使用に注意。
フランキンセンスがもたらす“内なる静けさ”
現代のように情報があふれ、心が常に動き続ける時代だからこそ、
フランキンセンスの香りは“静けさ”を思い出させてくれます。
呼吸が深まり、心が静まると、人は自然と本来のバランスを取り戻します。
それはまるで、忙しさの中で見失いがちな“自分の軸”を取り戻すような感覚。
ゆっくりと香りを吸い込みながら、内なる穏やかさを感じてみてください。
アロマテラピーサロンで行う「コンサルテーション」とは
2025/10/10
アロマトリートメントの前に行う「コンサルテーション」は、
お客様一人ひとりの心と身体の状態を知るための大切な時間です。
香りの感じ方や体調は日によって変化します。
その日の疲れ具合や気分、睡眠の状態、季節の影響――
小さな変化を丁寧に伺いながら、最も必要なケアを見つけていきます。
コンサルテーションで行う主な内容
体調や生活習慣の確認
・睡眠、食事、運動、女性周期などのリズム
・慢性的な疲れ、冷え、肩こり、肌トラブルの有無
・服薬中の薬や持病の有無(安全のために)
心の状態のヒアリング
・最近の気分の変化(落ち込み・緊張・焦りなど)
・リラックスしたいのか、リフレッシュしたいのか
・抱えているストレスや環境の変化
・好きな香り・苦手な香り
・嗅覚で感じる「今の自分に合う香り」の確認
当日のトリートメント内容の提案
・精油のブレンド内容
・施術部位や圧の強さ、時間配分の調整
・ホームケアのアドバイス(芳香浴、セルフマッサージなど)
コンサルテーションで大切にしていること
サロンでは、精油の香りをいくつか試していただきながら、
お身体の声や心のサインを一緒に探っていきます。
香りに「心地よい」「苦手」といった反応があるのは、
嗅覚が今の心身のバランスを映し出しているからです。
この反応を手がかりに、精油の薬理的作用と感情への影響の両面から
ブレンドを組み立てていきます。
なぜコンサルテーションが大切なのか
アロマトリートメントは、単に「香りで癒す」ものではありません。
心と身体のつながりを整え、自然治癒力を高めるためのケアです。
そのためには「今の状態を正しく知る」ことが欠かせません。
コンサルテーションは、
施術を“あなたに最も合う形”にカスタマイズするための準備であり、
同時に、ご自身の内側と静かに向き合う時間でもあります。
あなたのための香りを見つけるひととき
香りを選びながらお話ししていると、
「最近、こんなことで疲れていたんだ」と
ご自身の気持ちに気づかれる方も多くいらっしゃいます。
コンサルテーションは、ただの質問時間ではなく、
心をゆるめる小さなセラピーのようなもの。
そのひとときから、トリートメントの癒しが始まっています。
さいごに
香りの感じ方は“その日、その瞬間”のあなたを映します。
どうぞ気軽に、今のご自身を香りにゆだねてみてください。
あなたに最も合う精油とタッチで、
心身のバランスを整えるお手伝いをさせていただきます。
ベルガモット精油:柑橘の香りで、心をやさしく整える
2025/10/09
ベルガモットは、イタリア原産のミカン科の果実。
爽やかさの中にほのかな甘さを感じる香りで、気分を明るくしながらも穏やかに整えてくれます。
ストレスや緊張が続くとき、心が重たく感じるときにそっと寄り添ってくれる香りです。
主な作用
- ストレスや不安の緩和
- 気持ちを明るくリフレッシュ
- 消化促進(胃の不調にも◎)
- 皮脂バランスの調整(脂性肌やニキビケアに)
おすすめの使い方
- 芳香浴:
- トリートメント:
- アロマバス:
注意点
・光毒性があるため、肌につけた後は直射日光を避けてください(ベルガプテンフリーの精油は除く)。
・妊娠中は使用を控えましょう。
こんなときにおすすめ
- イライラや不安を感じるとき
- リラックスしたい夜に
- 優しい気持ちを取り戻したいとき
ベルガモットの香りは、“心をほぐす柑橘”とも呼ばれるほど穏やかで繊細。
落ち込んだときや緊張が続くときに、まるで陽だまりのような安心感を与えてくれます。
【秋の乾燥対策シリーズ・最終回】
まとめ&サロンのご案内
2025/10/06

これまで4回にわたり、「秋の乾燥対策」をテーマにお届けしてきました。
最終回は、そのまとめと、当サロンでできるサポートについてご案内します。
これまでの振り返り
1. 秋に乾燥が強まる理由
季節の変わり目は気温や湿度が急激に下がり、肌のバリア機能が低下しやすい時期です。
2. セラミドの役割と加齢による減少
肌の潤いを保つ鍵となる「セラミド」は、年齢とともに減少。外的刺激から肌を守る力が弱まっていきます。
3. 外から補うスキンケアとトリートメント
セラミド配合のパックや高保湿のスキンケアで、直接的に潤いを補給。
4. 内側から守る食事と生活習慣
大豆製品や発酵食品、睡眠やストレスケアなど、日々の習慣がセラミドを守ります。
秋の乾燥対策の考え方
外からの補給と、内側からのサポート。
どちらか一方ではなく、両方のバランスを意識することが、秋の肌を健やかに保つ秘訣です。
サロンでできること
当サロンでは、セラミドをたっぷり補給できるフェイシャルケアや、リラクゼーションを兼ねたアロマトリートメントをご用意しています。
ご自宅のケアに加えて、プロの手による集中ケアをプラスすることで、より一層潤いを実感していただけます。
この秋、乾燥知らずの肌で快適に過ごしていただけますように。
ぜひ一度、サロンケアを取り入れてみてください。
【秋の乾燥対策シリーズ④】
セラミドを守る食事と生活習慣で内側から潤いを
2025/10/06

秋が深まるにつれて、肌の乾燥が気になりやすくなります。
これまでのシリーズで「セラミドが肌の潤いを守る大切な成分」であることをご紹介しました。
今回はそのセラミドを“減らさない”“保ち続ける”ための食事と生活習慣についてお伝えします。
セラミドを支える栄養素
1. 大豆製品(豆腐、納豆、豆乳など)
大豆イソフラボンは女性ホルモンに似た働きを持ち、年齢とともに減少するセラミドのサポートが期待できます。
2. 発酵食品(味噌、ヨーグルト、キムチなど)
腸内環境が整うと、肌のバリア機能も安定します。腸とお肌は密接に関わっているのです。
3. 良質な脂質(オリーブオイル、アマニ油、青魚など)
オメガ3系脂肪酸は、細胞膜を柔らかく保ち、肌に潤いを与える役割があります。
4. 緑黄色野菜や果物(かぼちゃ、人参、柿など)
ビタミンA・C・Eは抗酸化作用を持ち、乾燥ダメージから肌を守ります。
セラミドを減らさない生活習慣
- 睡眠の質を整える:肌の修復は睡眠中に行われます。夜更かしや不規則な生活はセラミドの生成を妨げます。
- 紫外線・冷暖房から守る:秋冬でも紫外線や乾燥した空気はセラミドを減らす要因に。日焼け止めや加湿器を取り入れましょう。
- ストレスケア:強いストレスはホルモンバランスを乱し、肌の潤い不足につながります。香りを使ったリラックスもおすすめです。
まとめ
セラミドは「外から補う」だけでなく、「内側から守る」ことも大切です。
毎日の食事や生活習慣を少し意識するだけで、お肌は変わっていきます。
ただし年齢とともにセラミドは自然に減少していきますので、セルフケアだけでは限界も。
そんな時は、サロンでの保湿ケアで集中的にサポートするのがおすすめです。
【秋の乾燥対策シリーズ③】
セラミド不足を見極める — サインと毎日のセルフケア法
2025/10/06

秋は肌が乾きやすく、セラミドが不足しがちな季節です。
ここでは「セラミド不足の見分け方」と「家庭でできる具体的ケア」を詳しく解説します。
セラミド不足のサイン(セルフチェック)
以下の症状が当てはまる場合、セラミド不足の可能性があります。
- 洗顔後すぐに“つっぱる”感覚がある
- 目元・口元に細かい乾燥ジワが出る
- ファンデーションのノリが悪く、午後に崩れやすい
- 肌が粉をふく・カサつきやすい
- ちょっとした刺激で赤くなったりヒリつくことがある
これらは「バリア機能の低下=角質層の水分保持力の低下」を示すサインです。
なぜ今すぐケアが必要か
セラミドは年齢とともに減少します(20代後半から徐々に減り、40代以降で大きく低下することが多い)。
さらに秋の低湿度や夏のダメージが重なると、肌のバリアが脆弱になり、
乾燥→ターンオーバーの乱れ→くすみや小ジワへとつながります。
早めのケアで“乾燥の連鎖”を断ち切りましょう。
毎日のスキンケア・実践ルーティン(朝・夜)
朝(短時間で要点を抑える)
- 低刺激の洗顔(ぬるま湯・泡で優しく)
- 化粧水は押し込むように馴染ませる(重ね付け可)
- セラミド配合美容液を塗布(成分:セラミドNP/AP/EOなど)
- クリームで“フタ”(オクルーシブ成分:スクワラン、シアバター等)
- 日中は乾燥を感じたらミスト化粧水でこまめに保湿
- メイク落としは優しいタイプで(強い摩擦はNG)
- ぬるま湯で洗顔、タオルは押さえるだけ
- 美容液→セラミド配合のクリームでしっかり蓋
- 就寝前に表情筋をほぐす軽いマッサージで血行促進(血流改善は肌の再生を助ける)
週1〜2回の集中ケア
- やさしい酵素や低濃度AHAによる角質ケア(週1回が目安)
- シートマスクでのセラミド集中チャージ(10〜15分)
※刺激が強いピーリングは乾燥を悪化させることがあるので注意。
食事と生活面でできること
- バランスの良い食事(良質な脂質・たんぱく質)を意識:大豆製品、魚、ナッツなど。
- 良質な睡眠とストレス管理(自律神経を整えると肌回復がスムーズに)。
- 室内は加湿器で湿度を40〜60%に保つと肌の水分蒸発を抑えられます。
注意点(必ず守ってほしいこと)
- 熱い湯での洗顔・長時間の入浴はバリアを壊すので控える。
- 炎症が強い・ひび割れや出血がある場合は自己ケアを中断し、早めにご相談ください。
- 新しい製品はパッチテストを。
サロンでの補完ケア(プロの手で効率的に)
自宅ケアを補うために、当サロンでは
- セラミド配合の高浸透パック
- 血流を促すアロマボディ(巡り改善)
- ヘッドケアで自律神経を整えるトリートメント
を組み合わせた集中コースをご用意しています(10月限定クーポンをご参照ください)。
プロのトリートメントで“補う・守る・整える”を同時に行うことで、効果を持続しやすくなります。
まとめ&次回予告
セラミド不足は「気づきにくいが確実に進行する」問題です。
毎日の洗顔や保湿、生活習慣の見直しでかなり改善できますが、必要に応じてサロンの集中ケアを取り入れるのが最も効率的です。
次回(第4回)は「セラミドを守る食事と生活習慣」をご紹介します。
【秋の乾燥対策シリーズ②】
セラミドとは?肌の潤いを守る鍵
2025/10/05

秋の乾燥ケアに欠かせない成分のひとつが「セラミド」です。
セラミドは肌の角質層に存在する脂質の一種で、レンガの壁に例えると「レンガをつなぐセメント」のような役割。
細胞と細胞のすき間を埋め、水分を抱え込みながら外部刺激をブロックしています。
セラミドが不足するとどうなる?
セラミドが十分にある肌は、バリア機能が働き、潤いをしっかり守ります。
一方で不足すると、角質細胞のつながりがゆるみ、水分が蒸発しやすくなり、外からの刺激も入りやすくなります。
その結果として…
- 肌のつっぱりやカサつき
- 粉ふきやかゆみ
- 紫外線や花粉などへの敏感反応
- 小ジワやハリ不足
といった乾燥やエイジングトラブルが現れやすくなるのです。
年齢とともに減少するセラミド
セラミドは本来、私たちの肌に存在している成分ですが、残念ながら20代後半から少しずつ減少し、40代以降では半分近くにまで減るといわれています。
そのため、年齢を重ねるほどに「乾燥しやすい」「ちょっとした刺激でも赤くなる」といった悩みが増えてくるのです。
「乾燥=年齢のせい」ではなく、その裏にはセラミドの不足が関わっていることを知っていただきたいと思います。
セラミドには種類がある
セラミドには「ヒト型」「天然」「合成」などいくつかの種類があり、中でも「ヒト型セラミド」は人の肌に近い構造を持ち、浸透性や保湿力に優れているため、スキンケア成分として注目されています。
秋こそセラミドケアを
紫外線を受けた夏のダメージに加え、秋は気温・湿度の低下によってセラミドが失われやすい季節。
さらに年齢によるセラミド減少も重なることで、乾燥リスクは一層高まります。
だからこそ、この時期はセラミドを「補う・守る・増やす」ケアが大切です。
当サロンでは10月限定メニューにセラミド配合のパックを取り入れ、肌本来の潤いを抱え込む力をサポート。
乾燥にゆらがない、しなやかで透明感のある素肌へと導きます。
次回は「セラミドを守り、増やす生活習慣」についてご紹介します。
秋の乾燥対策シリーズ①
秋の肌トラブルはなぜ起きる?乾燥の原因を探る
2025/10/05

秋は気候も心地よく過ごしやすい季節ですが、お肌にとっては実は“乾燥の季節”の始まりです。
「夏が終わってホッとしたら、急に肌がカサついてきた」
「化粧ノリが悪くなってきた」
そんな変化を感じたことはありませんか?
その原因は、秋特有のさまざまな環境要因が重なっているからなのです。
夏の紫外線ダメージの蓄積
夏の強い紫外線は、肌表面だけでなく角質層にもダメージを与えています。
紫外線を浴びた肌はターンオーバーが乱れやすく、角質が厚くなったり、潤いを保つ力が低下したりします。
空気の乾燥と気温差
秋は一気に湿度が下がり、空気は乾燥し始めます。
さらに、昼夜の寒暖差も大きく、自律神経が乱れがちに。
その結果、血行が滞り、肌の代謝機能が落ちてしまいます。
生活リズムの変化
夏の疲れが出る時期でもあり、睡眠不足や食生活の乱れが続くと肌のバリア機能はますます低下します。
体も心も整っていないと、肌はすぐに乾燥や不調のサインを出すのです。
秋の乾燥を防ぐ第一歩は「原因を知ること」
秋に乾燥が進むのは「夏のダメージ × 秋の環境 × 生活リズムの乱れ」という複合的な要因によるもの。
だからこそ、肌ケアも“秋仕様”にシフトすることが大切です。
次回は「乾燥対策の主役・セラミド」に注目し、潤いを守る仕組みについて詳しくお話しします。
-
 1,8-シネオールの働きとは?ユーカリ・ブルーガムの機能性と活用術
ユーカリ属の中でも最も代表的なユーカリ・グロブルス(Eucalyptus globulus)。アボリジニは、葉
1,8-シネオールの働きとは?ユーカリ・ブルーガムの機能性と活用術
ユーカリ属の中でも最も代表的なユーカリ・グロブルス(Eucalyptus globulus)。アボリジニは、葉
-
 「ユーカリ ラディアータとは?」呼吸器サポートに最適な特徴・効果・おすすめの使い方
ユーカリの中でも最も“やさしい”タイプとして知られるのがユーカリ・ラディアータ。同じシネオール系ユーカリであり
「ユーカリ ラディアータとは?」呼吸器サポートに最適な特徴・効果・おすすめの使い方
ユーカリの中でも最も“やさしい”タイプとして知られるのがユーカリ・ラディアータ。同じシネオール系ユーカリであり
-
 ユーカリ・シトリオドラ精油|レモン香で肩こりケア・虫除けに人気のエッセンシャルオイル
ユーカリの中でも異彩を放つのがユーカリ・シトリオドラ。レモンのような心地よい香りが特徴で、主成分はユーカリ特有
ユーカリ・シトリオドラ精油|レモン香で肩こりケア・虫除けに人気のエッセンシャルオイル
ユーカリの中でも異彩を放つのがユーカリ・シトリオドラ。レモンのような心地よい香りが特徴で、主成分はユーカリ特有
-
 ジンジャー(Zingiber officinale)
― 冷え・巡り・消化を内側から整える加温ハーブ
ジンジャー(ショウガ)は、世界中で古くから薬用・食用の両面で用いられてきた植物です。メディカルハーブとしては、
ジンジャー(Zingiber officinale)
― 冷え・巡り・消化を内側から整える加温ハーブ
ジンジャー(ショウガ)は、世界中で古くから薬用・食用の両面で用いられてきた植物です。メディカルハーブとしては、
-
 クリスマスは、自分を大切にする日にしませんか
今日はクリスマスですね。街は華やかで、どこか気忙しい空気も感じる一日です。クリスマスは、家族のため、誰かのため
クリスマスは、自分を大切にする日にしませんか
今日はクリスマスですね。街は華やかで、どこか気忙しい空気も感じる一日です。クリスマスは、家族のため、誰かのため
Botanical Time
 お問い合わせは、WEBフォームにて受け付けております。
お問い合わせは、WEBフォームにて受け付けております。
所在地 :大阪府吹田市江坂町1-23-32 リバーボール江坂603
営業時間:10:00〜24:00
定休日 :不定休